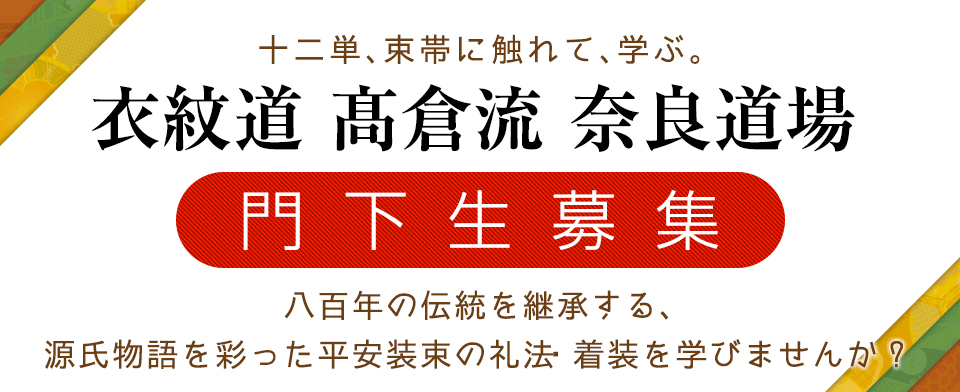
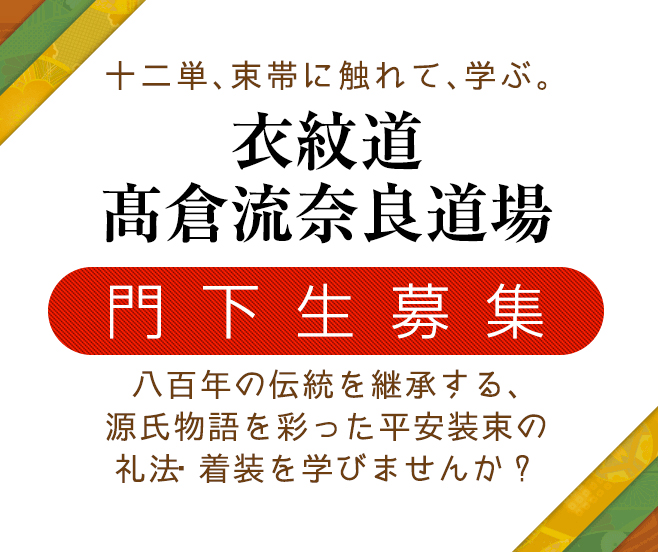
八百年の伝統を継承し、源氏物語などの平安文化を彩った装束(十二単・束帯)の礼法を学び、その着装の技術『衣紋道』に触れてみませんか?
有職故実にもとづく宮廷装束(十二単・束帯)に触れ、歴史の重みと宮廷の雅をぜひ全身で実感してみてください。また、宮廷装束など時代衣裳の着付けは、格式の高い婚礼や撮影など様々なシーンでの活用も期待されます。


平安時代に日本独自の発展を遂げた平安装束。その装束をより美しく、威儀を整え、着装する技術が「衣紋」であり、装束に関する有職故実の集大成が「衣紋道」です。
衣紋の創始者は後三條天皇の孫で「花園左大臣」(はなぞののひだりのおとど)と呼ばれた源有仁であるといわれており、その技術は鎌倉時代に山科家・高倉家に伝承され、天皇のお服上げの奉仕をしてきました。
明治16年(1883年)には、山科家・高倉両家に衣紋教授の命があり、以後装束の着装法は伝統として守られ、現在に至っています。
当・日本文化普及協会は、衣紋道髙倉流奈良道場として認可を受けております。
正式に宮廷装束の有職故実・着装をしっかり学び、技術を皆様と共有できる数少ない組織として、これからも八百年の伝統文化の継承に心して参ります。


衣紋道髙倉流奈良道場の入会費および年会費・授業料は下記の通りです。
| 入会金(DVD含む) | ¥20,000/初回のみ |
|---|---|
| 稽古着 | ¥37,800/初回のみ |
| 衣紋紐(2本) | ¥10,260/初回のみ |
| 年会費 | ¥10,000/年 |
| 授業料 | ¥10,000/1回4時間 |
奈良県奈良市大宮町6-9-1 新大宮ビル4F(日本文化普及協会事務局)
近鉄奈良線「新大宮」駅徒歩2分
なんばから約35分/梅田から約55分/三宮から約75分
見学ご希望の方は、下記のフォームよりご連絡ください。開講日程をお知らせいたします。 一度ご見学いただき、ご質問等あれば直接お答えしますので、充分にご納得いただいたうえでご入会ください。
※ご不明な点ございましたら、こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください
世界中で親しまれている「源氏物語」の絢爛優雅な世界が、壮大なスケールで現代に甦った「源氏物語/桐壺の巻」より、光源氏の元服の場面をイメージして、皇室・公家の成人式にあたる「加冠の儀」を平安時代の式次第に則って忠実に再現。儀式にふさわしい雅楽が演奏され、その出演者は総勢70人にもおよぶ華やかなステージでした。
これから葵上の成人式が執り行われます。

成人する女性は、初めて「裳」という着物を身につけます。

光君の「加冠の儀」を執り行うため、天皇が御簾の中で着座なさいます。

若宮の誕生を祝って、帝から「守り刀」と「産着の細長」を賜ります。

皇族出身である葵上の母君は、臣下に禁色が定められた白い「袿(うちぎ)」を着用します。

葵上は裳と唐衣を付けました。この姿を「十二単」と呼んでいますが、正式名称は「唐衣裳装束」または「女房装束」と呼ばれていました。

光君の「みづら」を解き、頭の上に「髷(まげ)」を作り、「冠」をお加えになります。
